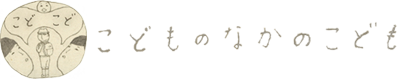Blog
客観性を無視したマスゲーム的コラム vol.4
いやいや久しぶりのコラムである。前回、書いてから日が経ちすぎて夏も終わってしまった。ポンピーの夏をふりかえると、やり残したことがいくつかあるような気がする。地球の温暖化くらい切実なものから、深爪くらいしょうもないものまで。
そのなかの1つをあげるとすれば、海に行けなかったことだろう。馬鹿みたいに晴れた空の下、うわの空でビーチボールをやりながら、真剣に女の子たちのビキニを見ることができなかったのは非常に残念である。海の家から聞こえてくるリップスライムやケツメイシやオレンジレンジなんかのノリの軽いラップを聴きながら、女の子たちの健康的な肌を見ることができなかったのは真に残念である。そんなに激しくない波に優しく揉まれながら、浮き輪につかまる濡れた女の子たちを見ることができなかったのはこの上なく残念である。冷やし中華より、花火より、蝉の鳴き声より大事な夏の風物詩、それが水着姿の彼女たちなのに・・・一生の不覚である。
そんな深爪くらいしょうもない後悔はさておき、今日の本題に入ろうと思う。実はと言えば、今日は大好きな村上春樹の最新刊を読んでいたのである。『東京奇譚集』という本なのだが、文字通り少し変わった内容の短編が5編入っている。あいかわらず読みやすく、なかなか趣きがあり、今のような秋口に読むにはちょうど良い本である。『風の歌を聴け』ほどおすすめでもないが、『アフターダーク』ほど貶すところもない本である。個人的には「偶然の旅人」という短編が肌に合い好感触だった。読む人もいると思うので内容は明かさないが、静かな雨が頭のなかに降り続くような内容である。
昨日、梅田の紀伊国屋でその本を買ってから今日の夕方までだらだらと断続的に読んでいたのだが、読んでいると色々なことを考えさせられた。村上春樹には珍しくそれほど内容に引き込まれることもなかったので、片手間に物思いに耽けっていたのだ。今日は、その短編集のなかの「日々移動する腎臓のかたちをした石」という短編を読んでいたときに考えていたことを書こうと思う。
そのとき考えていたのは、ポンピーがなぜ小説なんかを書こうと思ったのかということである。ポンピーが初めて小説を書いたのは大学1回生のときの正月である。正直なところ、それが正確な記憶かどうかはわからないが、その辺りである。題名も内容も考えずに、1年の始まりの寒い冬に、パパンからもらった古いワープロに慣れない手つきで衝動的に書き始めたのである。今では最初の一文に何を書いたのかさえ覚えていない。そのときはその出だしを書いた時点で、まるで世界平和をもたらしたかのように恐ろしく偉大なことをしでかした気分になったものである。ポンピーの自意識過剰が絶頂期を迎えていた時代である。そのため内容も超のつく個人的なもので、誰が読んでもコメントのしようがなかったと思う。(しかし出来上がったとたんに2人に読ますという鬼畜ぶりをティーンのポンピーはやってのけるのである)その被害者AとBが何とコメントを寄せたかは覚えていないが、二人とも「こういうのってよく分からないけど・・・」と前置きをしてからたどたどしい口調で感想を述べていたのは覚えている。まことに若気の至りすぎである。その頃はまだ村上春樹の作品も読んでいなかったため、文体はその当時に敬愛していた村上龍を意識したものだった。しかし今考えると、なんて無謀な冒険心と野心を持っていたのだろう、恥じらいや臆面なんて言葉を知らなかったのだろうか、と人格を疑わざるをえない。その無謀なティーンが書いた処女作は『フライング・マン』と題されている。この頃からポンピーはカタカナの題名が好きだったのだろう。今でもカタカナの題名に心惹かれる傾向にあり、本選びでも大きな判断基準になっている。
しかし不思議なことに、その作品を書き上げて間もなく、「なぜ自分は小説を書いたのだろうか?」という1つの疑問が生じた。たしかに衝動的に書かれた作品なのだから理由などないのかもしれないが、理由もなしにけっこうな量の活字を並べることができるだろうか。正直言って、ポンピーの歴史のなかに、作家になりたいとか、昔から本が好きだったとか、作文が得意だったとかいうような経歴はまったくない。その後、作家になりたいと思うことになったが、それにしても単純に働きたくなかったからである。ない頭をふり搾って考えたとき、作家ならなんとなく楽して生きていけそうだなと思ったのである。とてもではないが夢の出発点とは言い難い。
結局、その疑問はすぐに解消されることはなく、ポンピーのなかに不法滞在者として居すわることになった。それ以後も、この不定期のコラムのように、ときおり思い出してはお蔵入りし、またときおり思い出しては迷宮入りするといった具合に堂々巡りを繰り返した。
その終わりのない迷宮に光が射したのは大学4回生のときだった。その頃、ポンピーは大学の近くに下宿していてピザ屋のデリバリーをしていた。いかに短時間でピザを届けることができるかに命を賭けているバイク野郎が集まったイカ臭い職場だった。そのなかでマイペースに物思いに耽りながらデリをするのがささやかな気晴らしだった。バイト仲間に文句を言われることもあったが、結局のところ、外に出てしまえば勝手気ままだった。そんなデリバリーの時間を使って、ポンピーは将来のことや、小説の筋書きや、友達のことや、晩飯のおかずのことなど、ありとあらゆる物事について考えた。もちろんそのなかには長期不法滞在者となっていた謎も含まれていた。
ある日、夕方近くの薄暗い時間にデリバリーをしていたとき、ポンピーは思いがけずその長期不法滞在者を頭から追放することができた。それは一瞬の閃きだった。別に誰かが何かを言ったわけでも、周りの風景にヒントが隠れていたわけでもなかった。どういう思考の水路を巡って流れでたのかは覚えていないが、謎の答えは突如としてポンピーの頭に流れでた。
今思うと、その答えはもっと早くに見つかっても良かったような気がするが、きっと然るべきときがあって、その時期が来れば、ごく自然に解消される種類の謎だったのだろう。それがポンピーの場合、ちょうどある日の夕方近くだったのだ。
そして今日、「日々移動する腎臓のかたちをした石」という短編を読んでいるとき、不意にそのことを思い出してポンピーはこう考えたのだ。「どうしても解けなかったあの謎が解けたのだから、もしかしたら死ぬまでに、なぜ人は生きるのかという究極の命題でさえ解くことができるかもしれない」と。それは真実であるかもしれないし、あるいは大嘘かもしれない。だけどそういう考えに至ったことには意味があると思う。どういうところに意味があるのか具体的には説明できないので、これもまた不法滞在者としてポンピーのなかに居すわることになるが、こういった謎を持ち続け、ときおり解消することはきっと人生に花をそえる醍醐味なのだろう。
そしてポンピーは書きながらこう思うのだ。どうしてポンピーなんて無意味な名前を自分につけてしまったのだろうか、と。何を語っても嘘っぽく聞こえるじゃないか。ああ、一生の不覚であり、謎である。