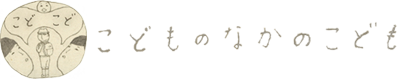Blog
客観性を無視したマスゲーム的コラム vol.9
関西人ってお笑いが好きだ。日曜日の昼間、家族団らんの時間に吉本新喜劇をテレビ放送しているのが多分に影響しているのだろう、とポンピーは分析している。
でも笑いが好きな分、当たり前なのかもしれないが、会話にオチを要求してくる人間が多い。そして話が長くなってくると、それに比例して話のオチも深くしなければならないし、そのあいだにコトバを噛むことも許されない。そういう十字架を生まれながらに背負っている。だからオチがないくらいなら話さないし、舌が回りそうにないくらいなら黙っている。見切り発車は地獄への片道切符だということを熟知している。
だから多くの関西人の会話は芸人じゃないのに芸人みたいなルールに縛られている。悲しい話にも、クソ真面目な話にも、笑えない話にも、定食についてくるたくあんのようにオチがついてくる。とにかく最後はなんでもいいから笑いを誘う必要がある、と思いこんでいる。
でも実際のところ、オチを気にしない人間もたくさんいる。そういう裸の王様みたいな奴を見ていると、ときどき羨ましくなる。主観的な統計によれば、そういう奴は女に多い気がする。笑いなんてなくたってTDLとテディー・ベアとケーキバイキングと甘い恋の話をしていれば女は満足なのだ。だからお客さま気分の女が多い。自分たちは散々オチのない話をしているくせに、こちらがそれに迎合して普通の会話をすると、体調が悪いのか、などとツッコミを入れてくれる。まるで評論家気取りだ。
だから女がボケて、それに男がツッコミを入れるというパターンのカップルや夫婦を目にすることは少ない。ある意味で、女がボケるというのは社会体制への批判であると捉えることができる。現存の社会体制では、男は仕事とボケ、女は家事とツッコミというパターンがスタンダードな愛の形なのだ。
だから男は小さい頃から、背が高くなりたい、格好よくなりたい、足が速くなりたいと願うのと同じくらい切なる思いで、オモロなりたい、と願っている。でも中学生くらいになると、自分が周りとくらべて笑いのセンスがいかほどのものなのかということが痛切に実感されてくる。そうなってくると平均以上の男は勇猛果敢にボケ倒し、平均以下の男は地方への引っ越しを人生プランとして考える。関西人はどんな奴でも地方に行けばオモロイ=人気者、という傲慢かつ単純極まりない方程式が土地の迷信のように根づいているのだ。全国の笑いのレベルをなめてるとしか言いようがない。
でもそれくらい男は笑いをとることに執着している。関西にいて、別に笑いなんてとホザいてる男だって「オモロいなー」が最上のほめ言葉だ。「ブサイク」と言われても生きていられるが、「オモんない」と言われると生きる権利を奪われたような気分になる。
日常的にそんな偏った価値観の世界で生活していると、たまにしゃべることが嫌になってくることがある。オチがないと不安でしかたなく、不意に最近自分がオモんなくなってきたかどうかを自問してしまう。英語を勉強してても実際に異国の地で話すときにボケれるかどうかを心配しているし、カラオケに行っても尾崎豊なんて素面では歌えない。ことさら女に告白するときは死に物狂いだ。好きだ、なんてストレートな言葉は死んでも言えない。あくまで笑いをメインに告白する。
「チャイコフスキーのチャイコフとってみてや」
「スキー。なに!?スポーツ!?」
とにかくお客さま気分の評論家気取りの女が多いから、細心の注意と斬新なボケがなければ口説き落とすことはムリだ。
「普通に告白したらええやん」
そういう女もなかにはいる。しかしそれでは後日、告白の経緯を友達に話したときに顰蹙(ひんしゅく)を買う。普通が怖いのだ。少しでも周りにオモロいと思われていないと表を堂々と歩けない。だからいつでも普通の男がただ普通に生活しているだけなのに、会話上は笑いに満ちた奇天烈な生活を送っている。嘘と誇張をふんだんに盛りこんで、普段の生活に強烈にスパイスを効かせている。だんだんと感覚が麻痺してきて、常に笑いの神様が自分の隣で微笑んでいるような錯覚に陥り、自分の等身大の生活を見失ってしまう。
それが文化だと言われれば返すコトバもないが、それでも正直な気持ちを言うと、そんな文化は消え失せてほしい。それが叶わぬ夢なら、体育の日や天皇誕生日のように国民の休日に笑いの休日を追加してほしい。そんな一日をつかって甘いコトバで恋人に愛を囁き、噛み噛みで政治について討論することができれば、残りの364日は労を惜しまずボケることを誓ってもいい。